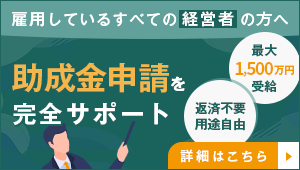米国のデジタル医療協会(Digital Medicine Society、略称はDiMe)は22日、ワシントンでイベント「Healthcare 2030」を開催した。同国のメディアであるMobiHealthNewsによると、政府高官、患者擁護団体、業界団体らが、デジタル医療について議論を交わすものになったという。
また、DiMeは論文「Healthcare 2030: An Impact Thesis for the Digital Era of Medicine」も発表。この中で、デジタル医療の関係者が追求すべき4項目が、取り上げられている。「データ」「コンピューティング」「コネクティビティー」「コミュニケーション」である。
これらの詳細を見ていきたい。
<PR>
医療保険について相談できるサイト
1.データ
データは、臨床データのみにとどまらず医療政策、医療費償還の支援、医薬品や医療機器の開発といった、医療に関するあらゆるデータを指すもの。これらを追求していくことによって医療のさまざまな面での進展が見込める。
DiMeは、こうした進展を促す技術の例として、センサーベースの医療機器やデジタルエグゾーストを挙げる。デジタルエグゾーストとは、デジタル空間に排出される情報のことで、医療では請求や電子医療記録が該当する。
医療と関わりの薄い人にとっては請求に関する情報と聞いても、ピンと来ないかもしれない。しかし日々、テック企業の動向を追っていると、AIと医療における請求のデータを結び付けたプロダクトなどを開発する企業が頻繁に見られる。増大し続ける医療費は各国で課題となっており、また米国のように独特の保険制度を有する国においては患者、医師・病院、医療保険会社の各社にとって請求データは重要なものとなる。
そしてDiMeは、データに関して言及する部分の最後に「単なる情報としてではなく、デジタル時代の医療における通貨としてのデータ」と締めくくっている。
<PR>
医療機関はもちろん動画や画像など大量のデータを保存している企業にも
2.コンピューティング
ここでのコンピューティングには、AIや複雑かつ高速なデータストリームが含まれる。コンピューティングによって、状況や事態のリアルタイムでの理解が可能となるとする。
そして、リアルタイムでの理解が専門家の意思決定を支援し、臨床医がデータに圧倒されず質の高いケアを提供できる。
<PR>
22万社以上が導入!法人向けレンタルサーバー『XServerビジネス』
![]()
3.コネクティビティー
医療機関の内と外とを結ぶコネクティビティー、すなわち、接続性を指す。医療機関の内外のコネクティビティーが高まることにより、患者は医療に関する情報が得られ、健康に結び付くであろう。
またDiMeは、コネクティビティーの高まりによってアクセス障壁の低減につながるとしている。米国の団体であるDiMeの立場からは、前述の保険制度の存在もあり、コネクティビティーによって予防につながり、消費者(患者)が高い医療費を支払わなくても済む、との期待があるのだろう。一方、へき地医療という意味合いでコネクティビティーは日本の医療にも求められそうだ。
さらに、患者、医師、研究者のインタラクション(相互作用)が、コネクティビティーにおけるフロンティアになっているとしている。
<PR>
医療機関だけでなくすべての企業の経営層・HRがチェックしておきたい厚労省の助成金
4.コミュニケーション
インフラが整った国であれば、医療においてオンライン診療が行われたり、メールによる非同期のコミュニケーションが行われたり、AIも使われたりしている。
こうした環境下で、DiMeが重要だと説くことの一つが、双方向の情報交換。先ほどのコネクティビティーと通ずるところだといえるだろう。もう一つ、トップダウン型の医療判断を動的で継続的なインタラクションに置き換えることも重要だとしている。
こうした取り組みが、提供するだけのケアではなく、理解され、パーソナライズされ、持続的なものに進化していくと説く。
<PR>
まとめ
DiMeはデジタル医療を、未来の医療を支える基盤であり、また医療の人間的側面(信頼や共感など)を良くしていく役割があるから、重要な手段であるとしている。また、本メディアとしてのまとめを述べると、DiMeはデジタル医療によって医師主体の医療から、医師や患者、その他の関係者が共同作業のように医療を進めていく方向へ転換していきたいとの考えを持っていると、感じた。
一方、デジタルというツールはこれまでも同様の期待がありながら、結局は一部のプロダクト、サービスの提供者が中央集権的に情報を握ってしまう状況を繰り返してきた。この点では、医療機器メーカーなどが「良心」を持った上で開発を進めていくことが期待される。